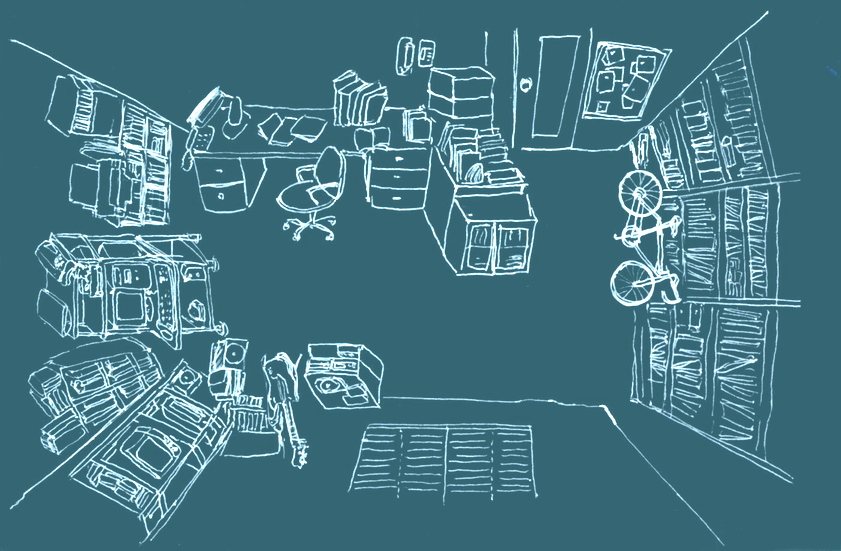性衝動を抑えないとトレポネーマの思うつぼだ。
トレポネーマとは梅毒を引き起こす病原菌、その梅毒が広がっているという。
Yahooは今年上半期に梅毒の患者が5000人を超えたことを伝えている。
“梅毒” の続きを読む
心肺蘇生
医師であり小説家であった渡辺淳一さんの短編集で病院が舞台の小説がある。救急室に運ばれてきた心肺停止した患者を医者たちが心臓マッサージを始める。しかし長時間やっても患者は蘇生せず、いつまで続けるかという話になり、結局「次にキリギリスが鳴いたらやめよう」という場面で終わるのだが、整形外科医だった渡辺淳一さんはあまり救急の場に接しておられなかったのかもしれない。
“心肺蘇生” の続きを読む
トランス脂肪酸
トランス脂肪酸のメモをしたのは6年前。今読んでいる「禍の科学」(ポール・オフィット著)にもトランス脂肪酸が出てきたので、その内容を交えて再度メモしてみる。
“トランス脂肪酸” の続きを読む
プリオン
医学生が行う解剖実習のご遺体にプリオン蛋白質が見つかったという長崎大学の報告があった。
プリオンは狂牛病の原因とされるもので、蛋白質なのに生き物のように自分を増やしていく不思議なものだ。
“プリオン” の続きを読む
禁煙警告
英会話アプリStudyNowで扱われていた話題。カナダで、もらいタバコで喫煙する人たちのために、タバコの害を喚起する対処を1本ずつしようという動きがあるという。そうしたひとたちはパッケージに書いてある注意喚起を読んでいない可能性があるからだという。
まだ検討段階らしいが、さてもし実行されるとなると一本のタバコになんと書く、あるいはなにを描くべきだろうか。
“禁煙警告” の続きを読む
「美しき免疫の力」
「美しき免疫の力」ダニエル・ディビス著 (科学者,サイエンスライター)を読み終えた。
院長の疑問と免疫学者の疑問は大きく異なる。
たとえば院長の疑問はなぜ桃太郎はスイカから生まれなかったのか。川を下るには桃より丈夫だと思うのだが、などというたわいのないものだ。
サル痘
サル痘が世界で流行り出している。診たことがないので調べてみると国立感染研究所に画像つきで経過の説明があった。
画像の説明は以下のようなものだ。
“サル痘” の続きを読む
音過敏
Highly Sensitive Person の勉強をした。いろんな感覚においても、あるいは対人関係で生じるいろんな気遣いにおいても過敏な人を指すようで、病名というよりは心理学的な概念のようだが、その状況を受け入れていることに結構なやんでおられる方もいるようだ。
“音過敏” の続きを読む
筋肉注射
コロナ予防接種の4回目が始まろうとしているが、接種の筋肉注射のやり方がこの日本では当初かなり混乱していたことは医療関係者以外あまり知られていないのではないか。
医者が集まるM3サイトでさえ注射をどう打てばいいのかという議論が沸き上がっていたし、最初厚労省が出した筋肉注射の説明ビデオもすぐに修正をされたほどだ。
“筋肉注射” の続きを読む
人体の細胞数
人体の細胞数はおおよそ60兆である。この数字、だれが調べたのか知らないが、と前置きし看護学校で生徒を前に口にした数字だ。
あらためて気になりその根拠をネットでを調べると、源流らしきものにたどり着いた。なんと大学入試の問題に出ているのだ。(https://tsuwamono.kenshinkan.net/way/pdf/14biology_02.pdf)
“人体の細胞数” の続きを読む