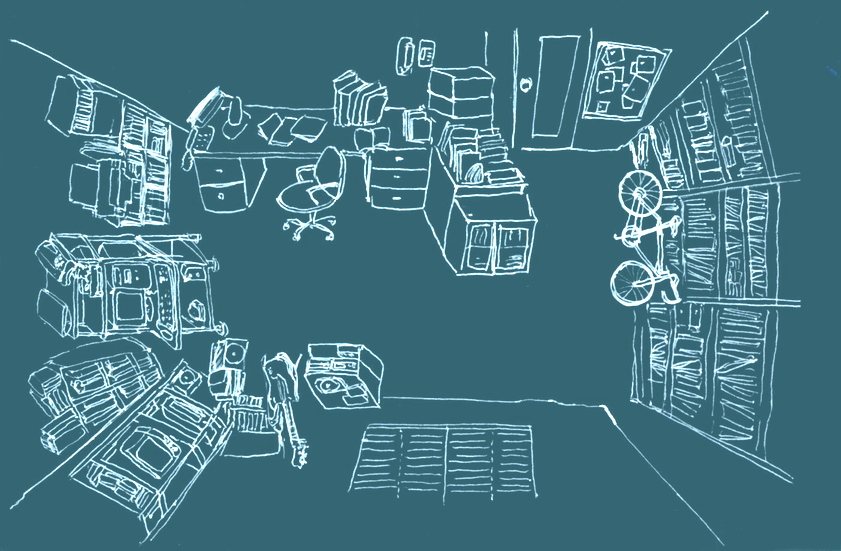「同志少女よ、敵を撃て」を読んだ。ボリシェビキの赤軍とナチスドイツとの戦いで赤軍の女性狙撃兵の活躍を扱った物語だ。主なモチーフは戦争での女性の性被害。
プロットがおもしろいだけでなく今起こっているウクライナの戦いを理解する上で地政学的にもとても参考になる小説だ。
だがそもそも敵とはなんだろう。
数十億年前、一個の細胞が誕生した瞬間から敵は存在する。ある意味、自分の成分とは異なる”敵”を区別するため細胞としてまとまったともいえる。
その細胞はさらに進化し、自己と非自己を区別したときの敵を免疫系で対処し、さらに生存競争における生物学的な敵を、たとえば早く位置を変えるなどの移動手段や擬態などの天敵から逃れる手段を獲得することで対処してきた。そして社会的な敵が出てくる。
ざっくり”敵”に関するこの俯瞰は間違っていないだろう。
そして、社会、すなわちやっかいな集団としての敵は戦争へと発展していく。
その戦争の形態はときどきの生産力に規定されるのは当然だ。つまり鉄器時代にはその武器に見合った戦いしかなく火器が出てきた時代もそれに見合った戦いしかないということだ。
今のウクライナの状況を見るまでもなく戦争における女性の性被害は続いている。ひょっとして古代の戦いから女性はこうした被害に合い続けているのだろうか。
わたしが男性だからかもしれないが、詳しく調べなくてもたぶんそうだと思う。どんなに戦争の形態が変わっても女性は性的被害者なのだ。
とすればとりわけ戦争という通常の社会ルールが変更されたときは、女性の敵は、男性すべてということだ。そしてこれは真実なのだろう。そういうことを前提に社会を見つめなおす必要があるのかもしれない。
もちろん戦争は反対だ。だが戦争の可能性はいつもある。そして戦争が起こるなら、「女の顔をした戦争」をしなくてはいけないのではないかと、読後に思う。