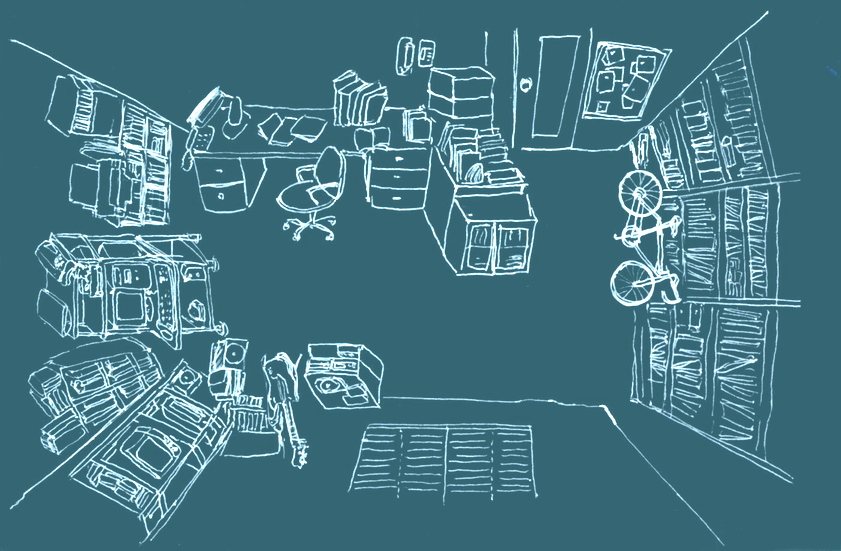幼な馴染みを思い出すのに誰しも馬鹿げた記憶のひとつや二つは伴うものだ。ましてや将来や人生を語り合うことなどできない年端も行かぬ子供にあってはむしろそれがすべてだろう
大きな洋装店を営む彼の家の3階だった
二人の前には小さな丸い蓋付きの容器がある。金属製のものでそっとその蓋を取ると生まれたての蠅がいた。数時間まえに捕まえたウジを数匹入れておいたのだ。二人は驚き、すぐにきゃきゃと笑いながらその場を離れる。どういうわけか金属の蓋の輝きがいつまでも残っていた。
幼いながらも彼の容姿にあこがれていた。似たような親の商売で、同じ商店街のなかにあったのも大いに影響があっただろう。多くの遊びの時間を共有し、つまりは一番の親友だった。そんな友だちとめったにない経験を共有できた満足感を抱いた、陽炎のような遠い遠い記憶。
だが、中学校に上がると連絡は疎遠になる。わたしが吹奏楽に没頭していたせいかもしれず、かれはかれなりに人生を真剣に考えていたせいかもしれない。
AIに尋ねると、こんな答えが返ってきた。
「金尾よしろう氏が天神のライブハウス「照和」で歌っていた時期について、正確な開始年は明記されていませんが、彼は「若いころは、博多の有名なライブハウス『照和』の常連ミュージシャンだった」とされています」
上京して音楽家として名をなしているとのことだったが、お互いの人生で交わることはなかった。ひょんなことで彼から連絡が来たのは何十年も経ってからだ。故郷にいる彼の父を診療したのを機に年始のあいさつが再開しーというのは幼いころも間違いなく交換しあっていたはずーていた。お互いの生存確認のような年賀の挨拶だったが、今年も送り、そして受け取っていた。
その彼が亡くなったと風のたよりに聞いた。
YouTubeで彼の生前の姿を追う。そのなかに故郷を謳った歌があった。
人の記憶が微かな光を放っているとすれば、きっと世界は仄かに輝いていることだろう。そして誰しもその人だけが見えるより輝きを増す光があるはずだ。
よっちゃん。君は、ふるさとに加え、無邪気だったころのあの輝きも見えていましたか。