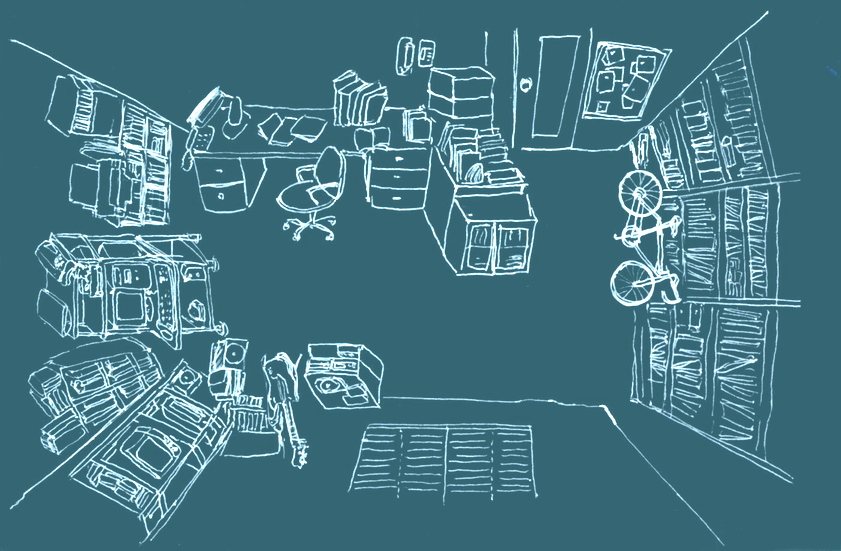「ベルリンは晴れているか」という本が書店で平積みしてあったので読んでみた。
戦後すぐの―まさに数週の‐ベルリンを舞台にした物語で、主人公の17歳の少女がある人物を探しあてるまでの2日間の過程を一人称で語られている。
正直、いろんな意味で圧倒された。
調べてみると作者は1983年生まれ。老獪という年齢にはとうてい達してないにも関わらず、第二次大戦前後の複雑な政治状況をよくとらえ、またそこに生きるひとびとの狡猾さをよくぞ表現できたものだと感心する。
いろんな糸が絡み合った物語だ。
ユダヤ人や少数民族への差別、ひととひとの憎しみの感情。幕間と称して過去を振り返る箇所には「夜と霧」を彷彿とさせるような記述があり、歴史の証言としてみても価値がある。
そして作者の意図は見事に、その題に表れている。
「ベルリンは晴れているか」‐戦争が終わり、混乱の中にただなかにあるとはいえ、ベルリンは晴れている。そう、ひとはそこでようやく日々の安寧をうかがうことができる。それにも関わらず主人公の心にはくすぶり続けて思いがあるのだ。心は晴れていない。
思うに人生とはそういったものなのだろう。
社会の大きな流れと個人が培う密な時間の流れ。ひとはそのなかを生きている。当たり前といえば当たり前だが、それぞれを関連付けて表現するのはむずかしい。
でも社会の流れが大きなうねりを見せた時、人は自分の流れを意識し、ときに明確な意思表示をする。たとえばナチ党にすり寄ったり、あるいは抵抗勢力として自分を位置づけることもある。コントラストがつき始め、ときにそれを物語ることができる。この本はそれをつづったものだ。
残念ながら時代の波が凪いでいるときは、それを意識できない。
自省するに、このくだらないメモはつまりはくだらないおやじの時間の流れを大きな軸としてとらえているだけだ。やはりそれではいけないと思う。
うずまくような社会の大きな流れに目を向けるべきだ。
だから今日のメモの詳細な題はこれにしたい。
加計、森友、厚労省、文科省、いったい疑惑は晴れているか